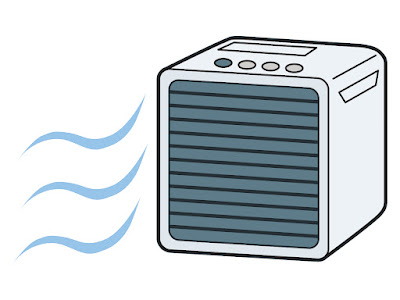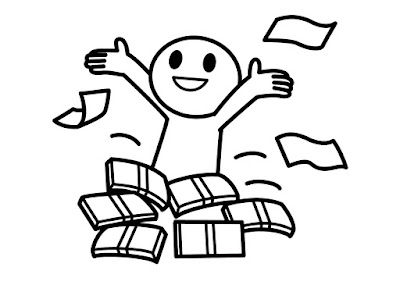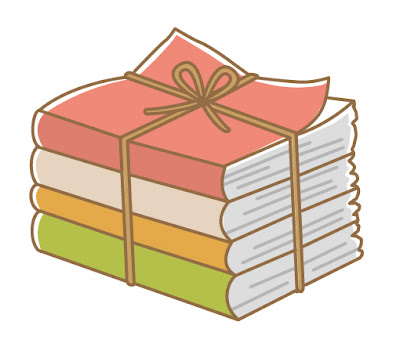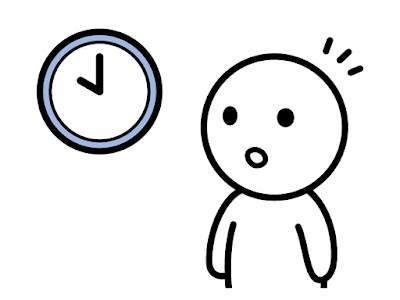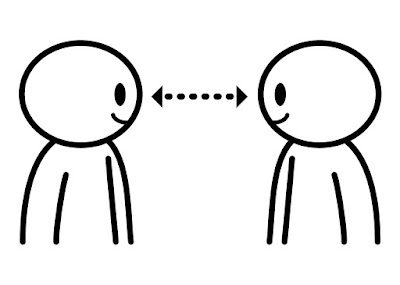食肉加工工場で学んだことが退職後の食生活で役に立った話

食肉加工工場で働いていたときは、人間関係の難しさや忙しい仕事、低賃金などに対する不満が多かった、詳しくは、 食肉加工工場で働いていた時に感じていた不満 を参照。 しかし、退職後に振り返ってみると、その経験から多くのことを学び、それが後の人生にプラスになっていると感じている。 手洗いの重要性 食品工場では、作業前やトイレの後、異なる作業を行う際に頻繁に手を洗うことが徹底されていた。 この習慣は家庭でも続けており、調理前や食事前にしっかりと手を洗い、アルコール消毒をしている。 コロナ禍においても、推奨されていたが、これらを継続することで感染リスクを下げることができたと感じている。 クロスコンタミネーション防止 生の肉や魚と野菜を同じ場所で扱わない、まな板や包丁を使い分けるなど、工場で学んだ知識を生かし、家庭内でも食材の交差汚染を防いでいる。 清掃と消毒の重要性 工場では、蛇口やドアノブ、証明や機械のスイッチなど、手が触れる場所の清掃と消毒が徹底されていた。 今でも家庭内で同様に清掃・消毒することを怠ってはいない。 特に、スマートフォンの消毒は重要だと考えており、定期的に行うようにしている。 有効期限の管理 工場で学んだ賞味期限や消費期限の管理方法を家庭でも実践している。 冷蔵庫や食品棚の中で、古いものを手前に、新しいものを奥に置くことで、食品ロスを減らす工夫をしている。 さらに、常に食べ切れる量の食材を購入することを心がけている。 ゴミの適切な処理 工場での廃棄物管理の経験を生かし、家庭でも生ごみやプラスチックゴミの適切な分別や処理を行い、衛生的な環境を維持している。 温度管理の徹底 工場での厳格な温度管理の経験から、家庭でも冷蔵庫や冷凍庫の温度を適切に設定し、食材の品質を保つ習慣が身についた。 虫や害虫の管理 工場での防虫・防鼠対策を生かし、家庭でも窓やドアの隙間をふさぎ、食品を密閉容器に入れることで、害虫や害獣の侵入を防いでいる。 最後に 食肉加工工場での経験を通じて学んだ衛生管理の具体的な方法は、家庭での食中毒予防や健康維持に大いに役立っ...