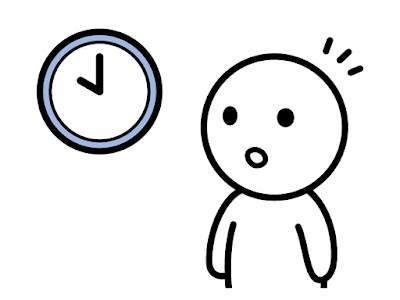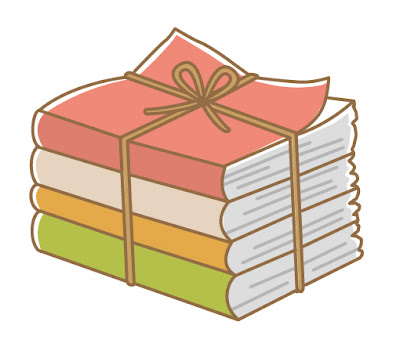「どうでもいい」という言葉が人間関係を壊す理由

世の中には「どうでもいい」という言葉がある。 似たような表現として「どっちでもいい」や「何でもいい」という言葉もあるが、これらは相手に選択の自由を与えているようでいて、同時にその選択を放棄するようなニュアンスを持っている。 つまり、「自分には関係ない」「選ぶのが面倒だ」伝えているようなものだ。 もちろん、これらの言葉が必ずしも悪いわけではなく、時には相手への気遣いや優しさとして使われることもある。 しかし、言葉のニュアンスが伝わらなかったり、誤解を招いたりすることもある。 自分でも無意識に使うことがあるが、他人に言われると腹が立つことも多い。 ということは、自分が使っているときも相手をイライラさせているのかもしれない。 だからこそ、これらの言葉を使うときは慎重になる必要がある。 「どっちでもいい」 腹が立つレベル:💢(怒りレベル1) 二択のときによく聞く言葉で、「どちらも同じくらい良い」という場合もあれば、「どちらにも興味がない」場合もある。 相手の意図が見えにくいため、少しイライラすることがある。 しかし、こちらに選択の自由を与えてくれているとも取れるので、そこは大目に見るのが得策だ。 もし相手が「どっちかに決めてほしい」と思っているのなら、面倒でも選んであげるのが無難だろう。 ただし、後から「やっぱり違うほうがよかった」と言われると、さすがに腹が立つ。 その時は「どっちでも同じだから」と軽く受け流すのがいい。 「何でもいい」 腹が立つレベル:💢💢💢(怒りレベル3) 特に「何を食べる?」と聞いたときに返ってくる言葉。 「何でもいい」と言われるとこちらが選ぶしかなくなる。 しかし、選んだ後に「本当は違うものが食べたかった」と言われると、理不尽さに怒りを覚える。 「何でもいい」と言うなら、本当に何を出されても文句を言わないのが筋だが、そうでないことが多いのも現実だ。 この状況を避けるためには、「何でもいい」と言われる前に、いくつかの選択肢を提示して選ばせるのが効果的だ。 手間はかかるが、人間関係の摩擦を減らすためには必要な対策かも知れない。 「どうでもいい」 腹が立つレベル:💢💢💢💢💢(怒りレベル5)...