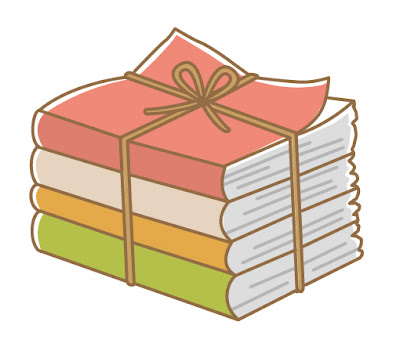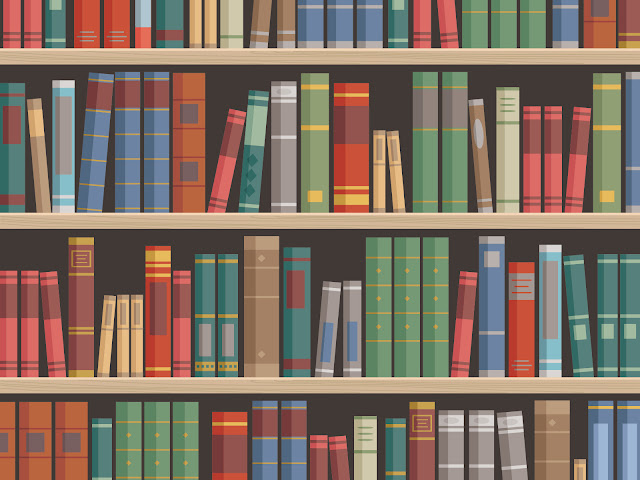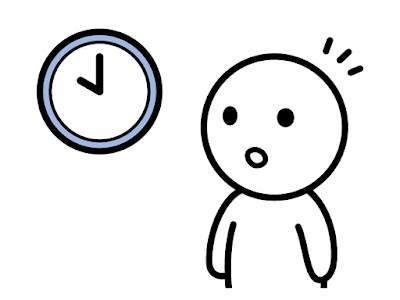「どうでもいい」という言葉が人間関係を壊す理由
世の中には「どうでもいい」という言葉がある。
似たような表現として「どっちでもいい」や「何でもいい」という言葉もあるが、これらは相手に選択の自由を与えているようでいて、同時にその選択を放棄するようなニュアンスを持っている。
つまり、「自分には関係ない」「選ぶのが面倒だ」伝えているようなものだ。
もちろん、これらの言葉が必ずしも悪いわけではなく、時には相手への気遣いや優しさとして使われることもある。
しかし、言葉のニュアンスが伝わらなかったり、誤解を招いたりすることもある。
自分でも無意識に使うことがあるが、他人に言われると腹が立つことも多い。
ということは、自分が使っているときも相手をイライラさせているのかもしれない。
だからこそ、これらの言葉を使うときは慎重になる必要がある。
「どっちでもいい」
腹が立つレベル:💢(怒りレベル1)
二択のときによく聞く言葉で、「どちらも同じくらい良い」という場合もあれば、「どちらにも興味がない」場合もある。
相手の意図が見えにくいため、少しイライラすることがある。
しかし、こちらに選択の自由を与えてくれているとも取れるので、そこは大目に見るのが得策だ。
もし相手が「どっちかに決めてほしい」と思っているのなら、面倒でも選んであげるのが無難だろう。
ただし、後から「やっぱり違うほうがよかった」と言われると、さすがに腹が立つ。
その時は「どっちでも同じだから」と軽く受け流すのがいい。
「何でもいい」
腹が立つレベル:💢💢💢(怒りレベル3)
特に「何を食べる?」と聞いたときに返ってくる言葉。
「何でもいい」と言われるとこちらが選ぶしかなくなる。
しかし、選んだ後に「本当は違うものが食べたかった」と言われると、理不尽さに怒りを覚える。
「何でもいい」と言うなら、本当に何を出されても文句を言わないのが筋だが、そうでないことが多いのも現実だ。
この状況を避けるためには、「何でもいい」と言われる前に、いくつかの選択肢を提示して選ばせるのが効果的だ。
手間はかかるが、人間関係の摩擦を減らすためには必要な対策かも知れない。
「どうでもいい」
腹が立つレベル:💢💢💢💢💢(怒りレベル5)
この言葉は、選択を放棄するどころか、会話や物事そのものを否定するような意味を持つ。
会話の途中で言われると、それまでの話の流れが一気に崩れ、こちらのやる気も削がれる。
ただし、文脈によっては「口を挟まない」「相手の意見を尊重する」という使い方もあるため、一概に悪い言葉とは言い切れない。
それでも、相手を傷つける可能性が高い言葉であることには変わりない。
個人的には、この言葉が大嫌いである。
人間関係を悪化させるリスクが高いため、自分では使わないようにしているし、言われそうな会話には触れないようにしている。
「どうでもいい」と言われないための対策
「いつでもいい」「どこでもいい」といった言葉も同様に、相手に選択を委ねているようで、実際には判断を放棄しているだけのことが多い。
こうした言葉を頻繁に使う人とは、いずれ意思疎通が難しくなり、人間関係がぎくしゃくする可能性がある。
それを避けるためには、最初からいくつかの選択肢を提示し、相手に具体的な決断を促すのが有効だ。
また、「どうでもいい」と言われても過剰に反応せず、「では○○にしよう」と自分で決めてしまうのも一つの手だ。
相手が本当に無関心ならそれで済むし、もしこだわりがあるなら、その時点で意見を言うだろう。
言葉の選び方が人間関係を左右する
言葉の使い方一つで、人間関係は大きく変わる。
「どうでもいい」や「何でもいい」といった言葉は、便利なようでいて、時には相手を傷つけることもある。
だからこそ、これらの言葉を使うときは慎重にし、相手の気持ちを考えた発言を心がけたい。
逆に、こうした言葉を頻繁に使う相手に対しては、適切な対策を取ることで、無駄なストレスを減らすことができる。
結局のところ、自分の心を守るのも人間関係を円滑にするのも、自分の言葉の選び方次第なんだと思う。
イラスト mine
2022.4.30 土曜日