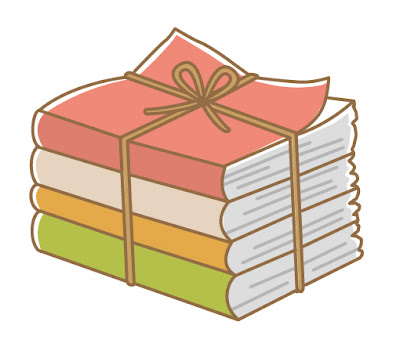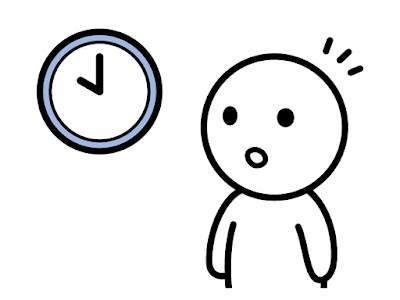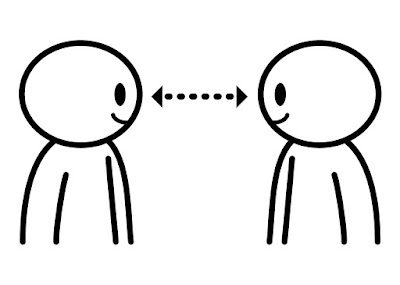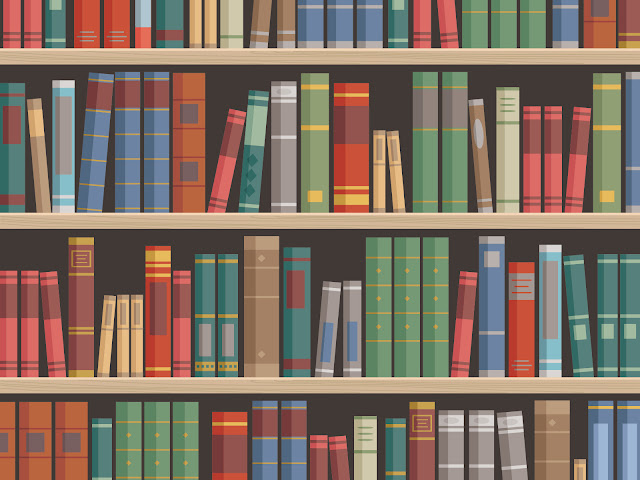他人を見返してやるための怒りとやる気

たまにだけど、過去の人間関係で腹の立つ出来事を思い出したとき、純粋な怒りが湧いてくることがある。 これは、過ぎ去った過去だからこその現象で、もしその過去から未来への影響を考え出してしまうと、単なる怒りから不安へと変わり、心に重荷がかかる。 だから純粋な怒りにはならない。 『純粋な怒り』って、どう説明したらいいかわからないけど、心が重たくならず、ただただ頭の中で怒りだけが渦巻いている状態だろう。 睡眠中の反芻(はんすう)は、怒りと不安が混じり合って心が疲弊して眠れなくなる。 でも、純粋な怒りだけなら、心の負荷はないから、ストレスとは違うものなのだ。 その純粋な怒りの先には、『見返してやりたい』という思いがある。 そして、自身の劣等感がその引き金となる。 だからこそ、単なる怒りではなく、『成長して相手を超えたい』という強いエネルギーが生まれるのだ。 その怒りが湧き上がると、不思議と『やる気』も一緒についてくる。 体がスタンバイの状態となり、後回しにしてきた面倒なことも、思わず手をつけたくなることがある。 しかもそのとき、見返してやりたい事柄と直接関係がないことでも、勢いで片付けられるから面白い。 ほとんどの人間は、他人よりも優位でありたいという生存本能を持っている。 単なる劣等感だけなら落ち込みで終わるだけだけど、『見返してやる』となれば成長が求められる。 つまり、純粋な怒りが成長への扉を開いてくれるのだ。 過去の屈辱、悔しさ、恥ずかしさを思い出したとき、もし純粋な怒りが湧き出してきたなら、それは単なるネガティブではない。 『強く、豊かに生きたい』という、自身の未来へのメッセージなのだ。 その怒りをうまく活用できれば、多様な挑戦ができ、自身の成長につながる。 もしかしたら、怒りという感情は単なる『闘争本能』ではなく、成長や進化を後押しする『生存本能』なのかもしれない。 そうして成長し、やがて寛大で心豊かな人となれば、過去のつまらない出来事など笑って受け流せるようになる。 いや、純粋な怒りの力で『人生を有意義』にできれば、それこそ最高の勝利なのではないだろうか。 イラスト:gontyan 投稿:2021.10...