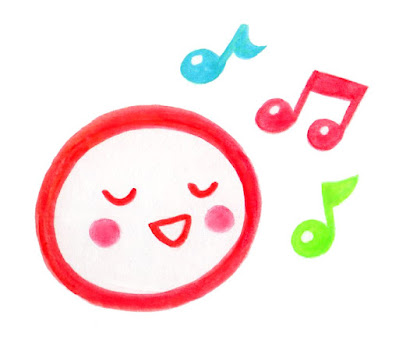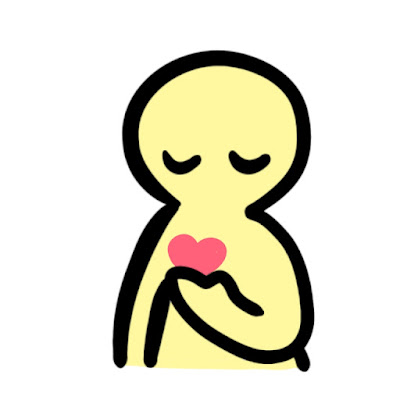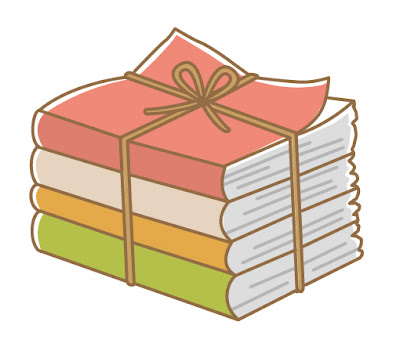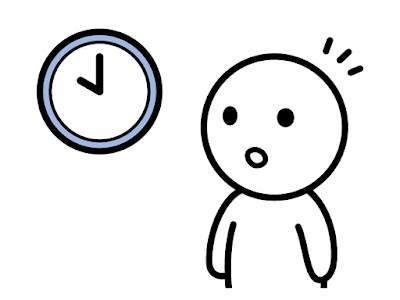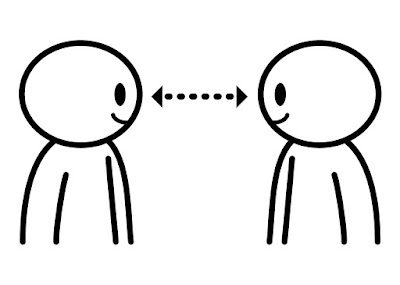断捨離がもたらす心と環境への影響

断捨離っていうのは、主に物理的なものを整理したり整頓したりすることを指すことが一般的みたいだけど、このプロセスが心にも深い影響を与えることがあるらしいんだ。 👀「へぇ~、断捨離って心にも影響を与える場合があるんだ」 ただし、これはすべての人に当てはまるわけではなく、逆にストレスや不安を引き起こす場合もあるから、けっこう個人差が多きいみたいだね。 👀「う~ん、物って自分のステータスみたいに扱っている人もいるから、そういう人にとっては物がないと落ち着かないのかな」 そうかも、あとは不要な物を手放すことで、頭の中が整理されるって感じる人もいるみたいで、そうすると過去の出来事や未来の心配事に縛られずに済むようになり、それが安心感に変わることもあるみたい。 👀「なるほど、頭の中が整理されると、心にも安心感をもたらすってことか」 ただし、これもあくまで一部の人にとっての効果で、誰にでもあてはまるわけではないんだよね、無理に断捨離を進めると、逆に過去の思い出や感情が強くなってしまって、かえって不安を感じる人もいるんだ……自分もどっちかというとそういうタイプかもしれない。 👀「過去の思い出か……大切なものもあるかもしれないからね……」 あとは、不要な物が減って周りが整然とすることで集中しやすくなり、注意力が散漫になることを防いでくれると感じる人もいるんだ。 👀「へぇ~、心地よく生産的な空間になることもあるんだね」 でもこれもまた、すべての人に共通する効果とは限らないんだよね、人によっては物が少なすぎて落ち着かなくなることもあるし、快適さの基準も人それぞれだから、自分に合った環境を見つけることが大切なんだ。 👀「ふ~ん、自分に合った環境を見つけることも断捨離の目的のひとつなんだね」 でも、過去の思い出や感情がつまった物を手放すのは、なんとなく寂しい感じもするよね。 👀「う~ん、だけど、過去に縛られているよりも現在と未来に焦点を当てたほうが心は楽になるのかもしれないね」 そうかもしれない……断捨離を通じて、何が本当に重要で、何が自分にとって意味のあるものなのかを見つめ直すい...