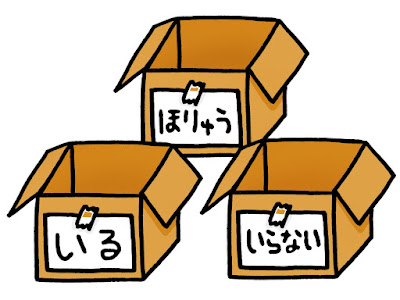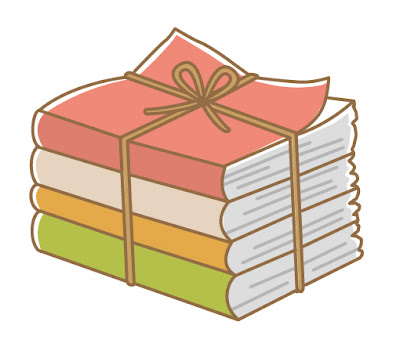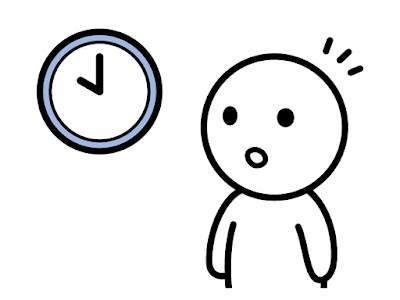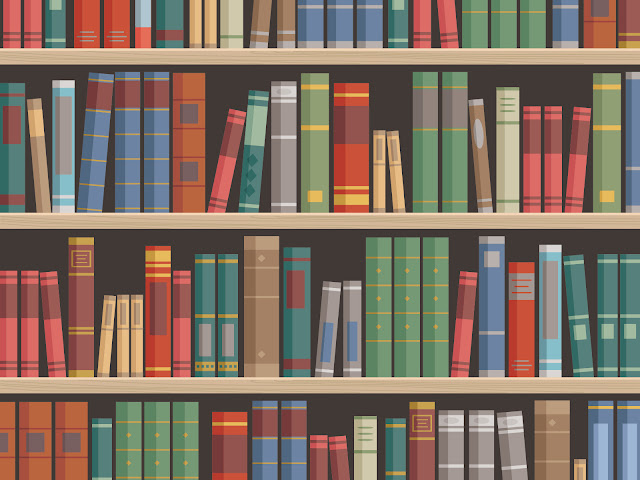もち米と普通の米の違いとは?

もち米とは、いわゆる「おもち」の原料になるお米のこと。 おもちはそのまま食べても十分においしいけれど、しょうゆもち、なっとうもち、のりもち、づんだもち、くさもちーーと、どれも絶妙にうまい。 お雑煮も大好きだけど、なかでも味噌ラーメンにおもちを入れるのが最高だと思っている。 おもちがスープにとけ込んで、ドロッとした雑煮風になったところに麺に絡む、あの食感がたまらない。 他にも、おこわやおはぎ、お団子のように、もち米とうるち米(普通のごはんに使うお米)を混ぜたものも好きでよく食べる。 うるち米とは普段の食事で食べるお米のこと。 さて、うるち米ともち米。 精米した状態で並べてみると、昔からずっと疑問に思っていたことがあった。 ーーなぜうるち米は炊く前に半透明なのに、もち米は最初からまっ白なんだろう?。 「白いということは、何か特別な栄養素が含まれていて、あのモチモチ食感を生んでいるのかもしれない」ずっとそんなふうに考えていた。 けれど、ある時ふと、「本当のところどうなんだ?」と思い立って調べてみた。 すると……驚きの事実が判明。 なんと、逆だった。 もち米には、うるち米に含まれている「ある栄養素」がないから、あの食感と白さが生まれていたのだ。 お米には「アミロペクチン」と「アミロース」という2種類のデンプンが含まれている。 うるち米はアミロペクチン80%、アミロースが20%の構成。 一方で、もち米にはこのアミロースがほとんど含まれておらず、ほぼアミロペクチンだけでできている。 たった20%の違い。 それだけで、あんなにも見た目も食感も違ってくる。 これは本当に驚いた。 「何かが多く含まれている」のではなく、「含まれていない」ことであのモチモチ感が生まれていたとは……。 もし、ふだんももち米を主食としていたら、うるち米のほうが「透明感があって、ちょっと固めで歯ごたえのある不思議な米」と感じていたのかもしれない。 日々意識していることがある。 それは、何事も一方向からだけ見ないということ。 「なぜだろう?」と問い直すことで、思い込みに気づき、本質が見えてくることがある。 人間関係だってそう。 「あの人はこういう人間だ」と決めつけるのではなく、自分が逆の立場だったら……と想像してみる。 ちょっと難しいけれど、それができれば、...