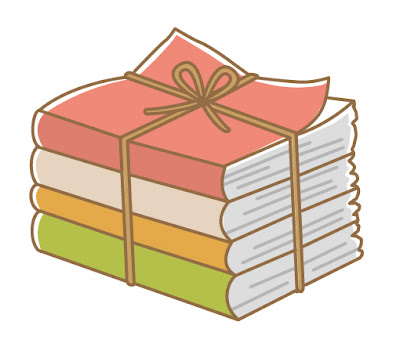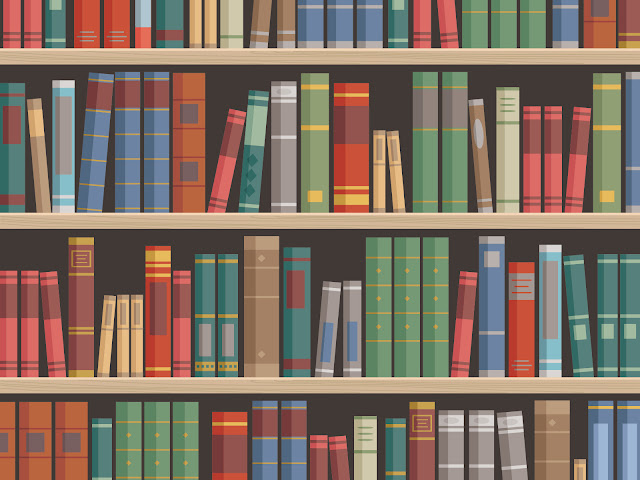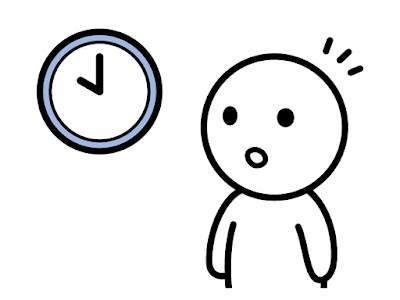なぜ税込み価格を小さく表示するの?
コンビニで買い物をしていると、いつも思うことがある。
それは……「値札の表示、なんでこんなんだろう?」ということ。
具体的に言うと、いまだに「本体価格(税抜き)」と「税込価格」の両方が並んでいて、しかも本体価格のほうが大きく書かれている。
そして、税込み価格は小さくて目立たたない。
これって、正直、ちょっと鬱陶しく感じる。
せっかく買い物しているんだから、気分よく選ばせてくれればいいのに、と思ってしまう。
セールをしないコンビニで、本体価格だけ強調されている意味って、あるのだろうか?。
最初は、「もしかして、ちょっとセコい販売戦略?」とかって思ってしまったが、でも、そんなあからさまなことを企業が堂々とやっているとも考えにくい。
気になったので、少し調べてみることにした。
安く見せるための心理的トリック
どうやら、税抜き価格を大きく表示するのは「少しでも安く見せたい」という販売側の狙いがあるようだ……なんじゃそりゃって感じだけど……。
人は視覚的に大きな数字に注目しやすく、その数字で価格を直感的に判断してしまう傾向があるみたい。
これを「プライス・アピアランス(価格印象効果)」と呼ばれてるそう。
たとえば、「920円」と書かれた商品があったとする。
レジでは消費税が加わって1012円になるが、目に入った「920円」の印象が強く残るため、無意識に「お得かも」と感じてしまう。
そんな効果を狙った表示だという……やっぱりこれか……。
なるほど、理屈は分かるけど、なんか、ねえ……。
でも、それって本当に消費者のためになっているのかって……なってるわけない。
メーカー表示との整合性を保つため
お菓子や飲み物など、一部の商品にはパッケージに「本体価格○○円(税抜き)」と表示されている商品がある。
これはメーカーが希望小売価格として定めたもので、店舗側もそれに合わせて値札をつけることが多いみたい。
たとえばメーカー表示が「本体価格100円+税 」の場合、店頭表示も「100円(+税)」になる。
こうした理由からコンビニのようにナショナルブランド商品が多い店では、税抜き価格がメインになりがちらしいけど……。
ただ、それでもやはり「実際に払う金額」が一目でわかる表示のほうが、親切なのでは?と感じてしまう。
店側の利益計算の都合
小売業では、売上や利益率、仕入れの計算はすべて税抜き価格を基準に行われている。
そのため、店内表示も税抜き価格が中心のほうが、業務的にはスムーズなんだとか……。
でも本当にそれだけが理由なんだろうか?。
というのも、商品によって、そもそも値札すらついていないこともある。
それなら、税抜き表示で管理しているという理屈は通らない気がする。
消費者としてできること
こうした背景を踏まえると、値札の表示方法にイライラするよりも、我々が「表示のカラクリ」を理解しておくことが大事かもしれない。
消費者として、以下の点に注意するようにしようと思った。
値札に書かれている価格が「税抜き」か「税込み」かを必ず確認する
小さく書かれている税込価格こそ、実際の支払い額なので見落とさない
セール価格も「税込でいくら安くなるのか」をチェックし、数字のトリックに惑わされないようにする
見抜く力が無駄な出費を防ぐ
税抜き価格を目立たせるのは、「安く見せたい」「メーカー表示と合わせたい」「利益計算上の都合がある」など、販売側の事情や戦略が背景にあるらしい。
もちろん違法ではなけど、消費者の誤解を誘いやすい表示であるのも事実である。
だからこそ「この表示にの裏には何があるのか?」と少し立ち止まって考える意識を持つことが大切なのだと思う。
ちょっとした意識で、余計な出費や勘違いを減らすことができるかもしれない。
投稿 2025.5.5 月曜日