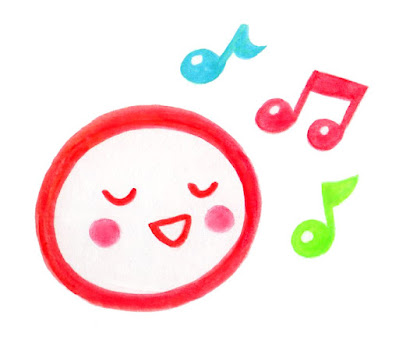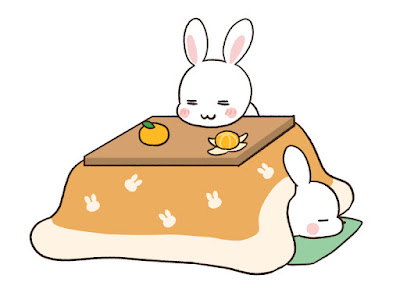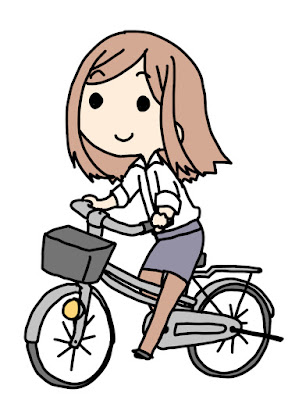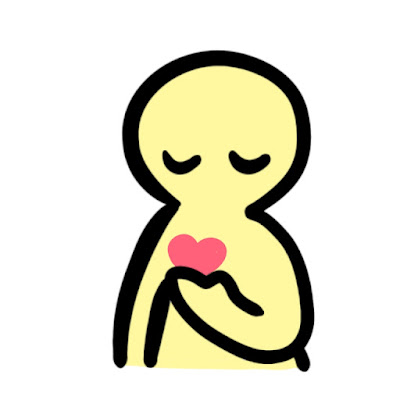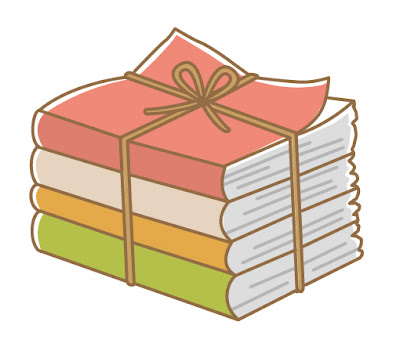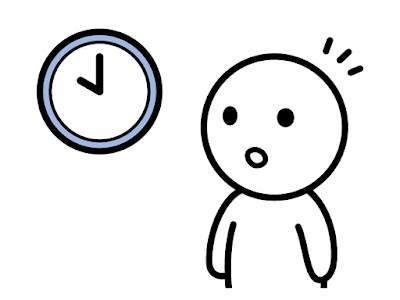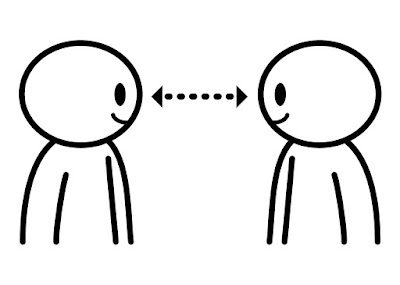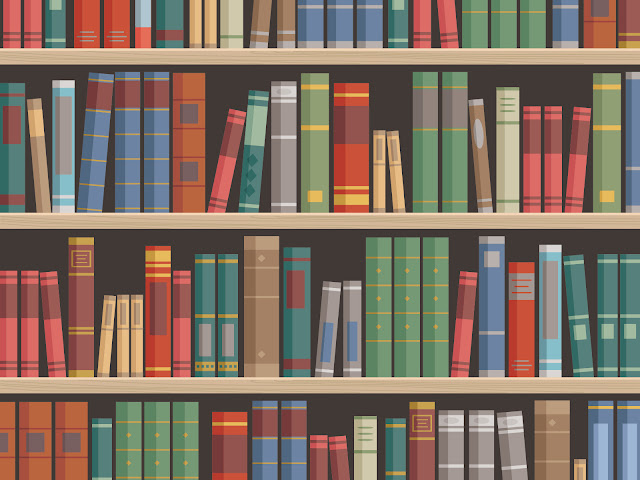元気が出た瞬間を大切にする

元気があるということは、人生にとって非常に有益なことだと思う。 元気が出たと感じた瞬間は、まるで心に光が差し込むような感覚だった。 疲れやストレスで沈んでいた気持ちが、ふとしたきっかけで軽くなり、前向きな気持ちに切り替わっていく。 友人との何気ない会話や、美しい景色に触れた瞬間、小さな成功体験があったときなど、さまざまな場面で元気が湧いてくる。 そのたびに、自分にはまだまだやれる力があるんだって実感し、再び頑張ろうという気持ちが強まっていく。 このように、元気が出る瞬間は意外なところに隠れている。 大切なのは、どんなに忙しい日常の中でも、自分をリセットする時間を大事にすること。 そして、ポジティブなエネルギーをもらえるような瞬間を見逃さないようにすること。 それが、明日への活力となり、さらに充実した日々を送るための原動力になる。 リセットする時間を設ける 日々の生活や仕事で蓄積した疲れやストレスを解消し、心身をリフレッシュさせるための時間を設ける。 現代社会では、忙しさに追われてしまいがちだが、自分のペースを取り戻し、リフレッシュするためには、このリセットする時間が非常に重要である。 リセットする時間の具体的な例として、次のようなものが挙げられる。 休息や睡眠 十分な休息や質の良い睡眠をとることて、体力と精神力を回復させる。 趣味の時間 自分が好きなことに没頭する時間は、ストレスを軽減し、心を豊かにする。 運動や散歩 体を動かすことで気分転換を図り、リフレッシュ効果を得ることができる。 瞑想や呼吸法 短い時間でも、心を落ち着ける瞑想や呼吸法を行うことで、心のバランスを整えることができる。 自然に触れる 公園や自然の中で過ごす時間は心を癒し、リフレッシュするのには最適である。 友人や家族との時間 大切な人たちとの楽しい時間を過ごすことで、心が安らぎ、エネルギーが湧いてくる これらの時間を意識的に持つことで、忙しさの中でも自分を見失わず、元気を取り戻すことができる。 投稿:2022.12.25 日曜日