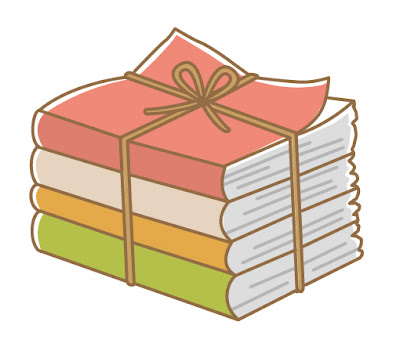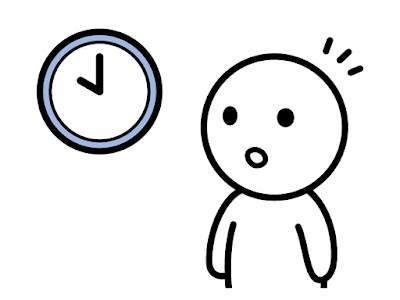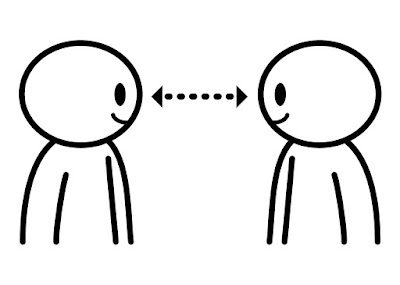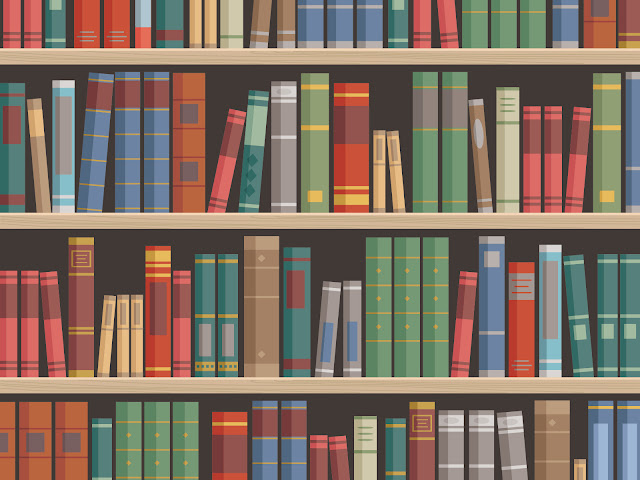価値とは何か~人が創り出すものの本質
道端に転がっている石ころに、「持っているだけで幸福が訪れるスーパーストーン」というキャッチフレーズをつけ、それを100円くらいの値段で売ってみる。
もし買った人が、望んでいたような幸福を得られなかったとしても、「まあ、100円だし」とあきらめるかもしれない。
けれど、もしそれを1万円で売ったとしたら……期待が大きくなるぶん、効果が感じられなければ「これは詐欺じゃないか?」と思う人も出てくるかもしれない。
この例からもわかるように、人は「価格」によって、その物の価値を感じやすい傾向があるのかもしれない。
高いから良いものに見えるし、安いとたいしたことがないと思われがちだ。
「そんなものには引っかからない」と思う人もいるだろうが、実際の世の中には、もともと価値がなかったものに「価値がある」と誰かが言っただけで、驚くほど高額で売れてしまうものがたくさんある。
価値は植えつけられる
物心がつく前の子どもは、たぶん「価値」というものをまだ知らない。
ただ、本能的に母親や世話をしてくれる人に安心や必要性を感じるくらいだろう。
でも成長していくうちに、周囲の大人たちの反応や社会の空気を通して、さまざまなものに「価値」があると学んでいく。
もともと自分にとってどうでもよかったものにも、「これは大事なんだ」と刷り込まれる。
そうして価値観は少しずつ形づくられ、人それぞれ違った「大切なもの」を持つようになる。
価値の決まり方
世の中では、「誰でもできること」「すぐ手に入るもの」「劣化しやすいもの」には、価値がつきにくい。
逆に、「時間がかかる」「手間がかかる」「希少性がある」「特別な資格が必要」などの条件がそろうと、高い価値がつく傾向がある。
こうした基準で、世の中のものやサービスの価値は決められている。
虚構の価値に支えられた社会
千円札には「千円の価値がある」と信じているからこそ、みんなが使っている。
でも、よく考えてみれば、紙切れ一枚が千円の価値を持つなんて、不思議な話だ。
物の値段は、原料の入手しやすさ、作るまでの手間、流通経路などによって決められている。
けれど、それらの基準自体が人間が勝手に作ったルールにすぎない。
つまり、絶対的な価値なんて、どこにも存在しない。
それでも、みんながその「虚構の価値」を信じているからこそ、社会は成り立っている。
価値は創造できる
冒頭の石ころの話に戻ろう。
もし誰かがその石を手に取った瞬間、偶然いいことが起きて「これは本物かも」と思ったら……その石には「本当に価値がある」と感じるかもしれない。
つまり、もともと価値のなかったものに、あとから人が意味を与えることで、価値が生まれるのだ。
こうして世の中では、これまでも多くの「虚構」が作られ、そのたびに新しい価値が生まれてきた。
これからも、新しい虚構が作られるたびに、我々は新しい価値を信じていくことになるだろう。
価値がある人間とは
会ったこともない人に「価値がある」と感じることは、あまりない。
でも、その人が何かをやり遂げたとか、長い間努力を続けていると知れば、「この人には価値がある」と思うこともある。
世の中では、よく「お金を持っている人」や「地位のある人」が価値のある人として扱われがちだ。
でも、結局のところ「誰にとって価値があるのか」は人それぞれ違う。
だから、「本当に価値がある人とは誰か?」という問いに、正解はないのかもしれない。
自分の価値を思い出す
大切な人や、愛するものに価値を感じるのと同じように、本当は「自分自身」にこそ、何よりも高い価値がある。
たとえ何もできなくても、何も持っていなくても、「今、生きている」だけで、もう十分に価値がある。
そう気づけたとき、自分という存在そのものが、何よりも尊いものに思えてくるかもしれない。
必要以上に「他人がつけた価値」に振り回されず、自分自身の感覚で「何が大切か」を見極めていくことが、これからの時代を生きるうえで、もっとも大事なことかもしれない。
投稿:2021.11.15 月曜日